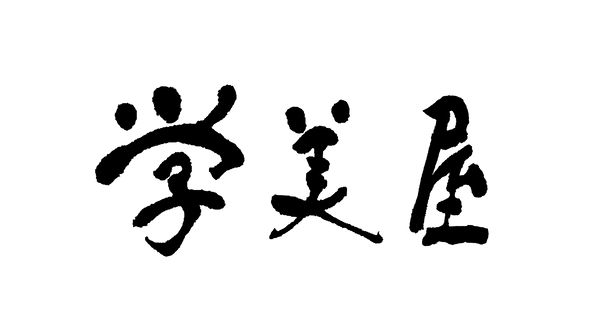いいコスメと出会うために身につけるべき習慣。この習慣で人生が変わる。
Share
はじめに
「〇〇が販売しているから・・・」
「〇〇が使ってるから・・・」
「〇〇が宣伝してるから・・・」
上記の理由でコスメ選びしてませんか?
それだと、「本質的にいいコスメ」に出会える確率はググっと下がります。
流行や広告よりも頼りになるのが成分表。
美容コスメ(医薬部外品はまた別)においては、「すべての答えは成分表に書かれてます。」
基本ルールをおさえ、“見る習慣”をつけるだけで、ムダ買いはグッと減り、いいモノと出会えます。
本記事は成分表の実践的な読み方と習慣化のコツをまとめました。
成分表の大前提ーここだけは知っておく
-
全成分表示が義務化:日本では化粧品に配合された成分をすべて表示します。名称は日本化粧品工業連合会(JCIA)のリストなどに基づく邦文名が推奨されています。厚生労働省+1
-
並び順は“多い順”:基本は配合量の多い順。1%以下の成分と着色剤は順不同でOKという例外もあります。後半の順序は目安と覚えておきましょう。厚生労働省
-
海外でもほぼ同様:EUや米国FDAも「多い順」+「1%以下は順不同」の考え方で整合しています。(細部の規定は各法令を参照)。Public Health+2U.S. Food and Drug Administration+2
-
INCI名ってなに?:国際的な成分名ルール。欧州のCosIng(※)や日本の表示名称リストで調べられます。「トコフェロール=ビタミンE」など、慣れると対応関係がつかめます。ウィキペディア+2single-market-economy.ec.europa.eu+2
※ CosIng(コーシング)は、欧州委員会が運営する化粧品成分のデータベースのことです。
まず“ここだけ”見る 3ステップ
ステップ1
先頭〜上位5〜7成分をチェック
最初に並ぶのは“中身の大部分”。水・グリセリンなどのベース、次にオイルや保湿成分が来ることが多いです。「推し成分」がかなり後ろなら“ほんの少量”の可能性も。
U.S. Food and Drug Administration
ステップ2
保湿・守る成分があるか
ヒアルロン酸、セラミド、スクワランなど“うるおい”に関わる定番が入っているかを確認。肌悩みに直結するため、まずはここから。
※配合量や処方全体との組み合わせなどで体感は変わります。
ステップ3
苦手成分の“自己防衛”
アルコール(エタノール)、香料、着色料など自分が苦手だったりアレルギー経験のある成分を把握しておくと、購入前に回避できます。
香料は「香料/Fragrance」と一括表示されることがあります。
厚生労働省
よくある勘違い
-
「上位=効果が強い」ではない
“量の多さ”と“働きの強さ”は別。ごく少量で役割を果たす成分もあります(例:防腐・キレート剤・pH調整剤など)。
-
“1%ライン”以降は順不同
後半の順番に意味を求めすぎない。むしろ“入っているか/いないか”を確認。 厚生労働省
成分表リテラシーを育てる「習慣化」レシピ
習慣1:買う前に“名前で1分検索”
商品名+「成分名」で検索→CosIngやJCIAの名称リストでざっくり確認。用途・別名・制限の有無が分かります。
single-market-economy.ec.europa.eu+1
習慣2:手持ちコスメの“上位5成分”を書き出す
ノートやメモアプリに上位5〜7成分だけ列挙。複数品を並べると、自分が好きな“処方の傾向”が見えてきます。それがいいか悪いか「成分的な観点のみ」で判断してみましょう。
習慣3:同カテゴリ商品を“成分表くらべ”してみる。
化粧水なら化粧水を3つ並べ、違いが出る箇所(溶剤・保湿骨格・防腐系)にマーカー。広告より“中身”で比べる癖がつきます。
!!最重要!!
習慣4:苦手成分、避けたい成分、避けるべきリストを携帯のメモに作る
肌トラブル経験がある成分名を自分辞典に。買い物中にサッと照合すればミスマッチを減らせます。
この確認作業をしているうちに、「成分名」覚えるのでこのメモはそのうちいらなくなります。
まとめ
成分表は“読むコツ”さえ掴めば難しくありません。
多い順/1%以下は順不同という大原則をおさえ、
先頭〜上位と苦手成分の有無をチェックする習慣をつければ、
広告に振り回されない“自分基準”が育ちます。
今日から**「まず成分表をみる」**を合言葉に、ムダ買いゼロ、本質的にいいコスメ選びへ。
補足・参考URL
-
厚生労働省|全成分表示の表示方法(1%以下は順不同 等) 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta7768&dataType=1&pageNo=1 -
日本化粧品工業連合会|成分表示名称リスト(邦文名/INCIの検索) jcia.org
https://www.jcia.org/user/business/ingredients/namelist -
日本化粧品工業連合会|成分表示ガイドライン概説 jcia.org
https://www.jcia.org/user/business/guideline/ingredientlabelling -
欧州委員会|CosIng(EU成分データベース) single-market-economy.ec.europa.eu
https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/cosmetics/cosmetic-ingredient-database_en -
EU規則 1223/2009(PDF)|EU化粧品規則(成分表示の根拠) Public Health
https://health.ec.europa.eu/system/files/2016-11/cosmetic_1223_2009_regulation_en_0.pdf -
米国FDA|Cosmetics Labeling Guide(成分は多い順) U.S. Food and Drug Administration
https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetics-labeling-regulations/cosmetics-labeling-guide -
米国FDA|Cosmetic Ingredient Names(国際市場向け表示の考え方) U.S. Food and Drug Administration
https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetics-labeling/cosmetic-ingredient-names